関西医科大学 ITからみた医療・医学 A1(分担:情報活用の理解(1))
(医学部医学科)
開講にあたって
https://medbb.net/education/2025init/
困った時,オンラインでのサポートやなにかありましたら上記サイトからご連絡ください
授業の到達目標
情報・科学技術を医療に活用することの重要性と社会的意義を理解する。医療における情報・科学技術に関連する規制(法律、ガイドライン等)の概要を理解する。
科学と技術と科学技術と
科学
性質や現象について経験的に論証できる理論を取り扱う分野科学の基本的な条件としては,実証性,再現性,客観性
技術
原理や理論を実際に適用する手段を取り扱う分野科学技術
科学及び技術のこと科学に基づく理論を取り入れた技術もあれば,技術の進展によって新たな科学的な知見を得られるケースもある
世の中には未だ(これからも)科学的に証明されていない技術が存在する
生活者の視点だと流通している食材は安心安全な食材で科学的に検証されている(=故に科学は正しい)と捉えてしまうように思います.「フグの卵巣」は科学的に証明されていない手法で,安心安全な食材として流通しています
一般的に技術=科学技術と置き換えてしまっているように思いますが,科学で説明できない技術に基づくものは社会に存在します.
当然ながらその技術も正しく使わなければ安全な食材にはなりません
世の中全てを科学で語ることができたならば,それはより良い未来に繋がるだろうと思いますが,世の中そんなに甘くないというところですかね
<参考>
「科学」と「技術」、「科学技術」について(21世紀の社会と科学技術を考える懇談会(第3回) 科学技術庁 科学技術政策局)
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kagaku/kondan21/document/doc03/doc36.htm
小学校学習指導要領解説(文部科学省)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1387014.htm
【理科編】小学校学習指導要領(平成29年告示)解説(文部科学省)
https://www.mext.go.jp/content/20211020-mxt_kyoiku02-100002607_05.pdf
世界の珍食一位猛毒「フグの卵巣の糠漬け」(東京新潟県人会)
https://kouhou.niigatakenjinkai.com/?p=2835
COREZOコレゾ「自分に抱え込もうとすると、水は溢れ出し、外に押し出せば、水は自分のところに流れ込んでくると、郷土の伝統食品、ふぐ卵巣ぬか漬を守り続ける七代目」賞(一般財団法人コレゾ財団)
https://corezoprize.com/araki-toshiaki
No.19001 フグ(卵巣)による食中毒(H-CRISIS 国立保健医療科学院)
https://h-crisis.niph.go.jp/archives/136651/
情報
戦争に関する本で翻訳する時の森鴎外による造語とされる
COVID-19流行期における保健医療と情報-ICTによるディスタンスコントロール- より
情報周辺の関係を整理すると

データ
ノイズとして認識しなかった事柄の記録発生するデータは受診特性に依存する.
一次データと二次データに分けられる
一次・・・対象からダイレクトに取得
二次・・・既に記録されたもの。まとめられたもの
情報
データに意味を付与したもの情報化にあたって受信者の特性に依存する.
知識
情報を体系化したもの。受信者の知性に依存する.
その時点での受信者の知識によるところが大きい
情報の非対称性
医療の場合は医療提供者側と受療者側の有する情報に差が生じてしまうここでは受療側と医療提供側に分けてまとめたほうが全体像が見やすくなるかなと思い設定しました
受療側にとって医療機関は「非日常の場」であり,自身では困難な日常生活を取り戻すことを託している
その結果として受療側から奇跡な出来事に感ずることが起こるものの,医療提供者側にとっては日常 と ものの事実に対する解釈は全く異なる
患者さんと医療従事者の微妙なバランス(職種によってもバランスが違うように思う 特にライセンス上医師には多大な権限を有していることから気をつけないと全体像を見誤るかもしれない
全体像を意識して,大学病院での研修から離島研修まで様々な経験をしていただけたら良いかと思います
(学生と教員の関係も情報の非対称性が存在するわけですが,良い経験と思って学修に取り組んでください)
データのメタ化
メタ化とは,データに様々な情報(二次データ)が付加されたもので,具体的な事実から解釈(=情報化)に向かっていくテキストデータに医用画像の位置情報を付与して表示させた例

産学官連携マネジメント論2018(分担:地域医療と産学官連携)より
保健医療分野における住民側の情報活用
医療機関の選択
医療機関からの発信
旧来のメディアでは広告や看板で存在を告知医療機関のTVCMなどをご覧になれば,他の業界のCMとの違いから規制の厳しさを想像できるかと
youtubeで「医療機関 CM」で検索した結果
https://www.youtube.com/results?search_query=%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%A9%9F%E9%96%A2%E3%80%80CM
当初インターネット上のWebサイトについては広告規制の対象外だったが,現在は広告規制の対象となっている
医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/index.html
行政からの発信
医療機能情報提供制度に基づいて,住民の医療機関に資する情報提供を都道府県単位で実施されている医療機関から都道府県知事への報告を義務付け,報告を受けた情報を住民・患者に対し分かりやすい形で提供する制度として運用していた
↓
全国統一的な情報提供システム(医療情報ネット)を構築し、令和6年4月から運用を開始
問1 なぜ都道府県単位で情報を集約していたのか?
住民からの発信
実空間における井戸端会議(口コミ)が支配的

SNS時代における個人情報保護と情報セキュリティ より
インターネットの普及で口コミが拡散する時代に

データ共有と分析で実現する産婦人科病院に役立つ指標の作成 より
問2 顔の見える口コミに対して顔の見えない口コミの利点と欠点について考えよ
保健医療分野における提供側の情報活用
診療で発生した情報の利用
カルテ
法令で「カルテ」なる言葉は出てこない「診療録」のことを指す
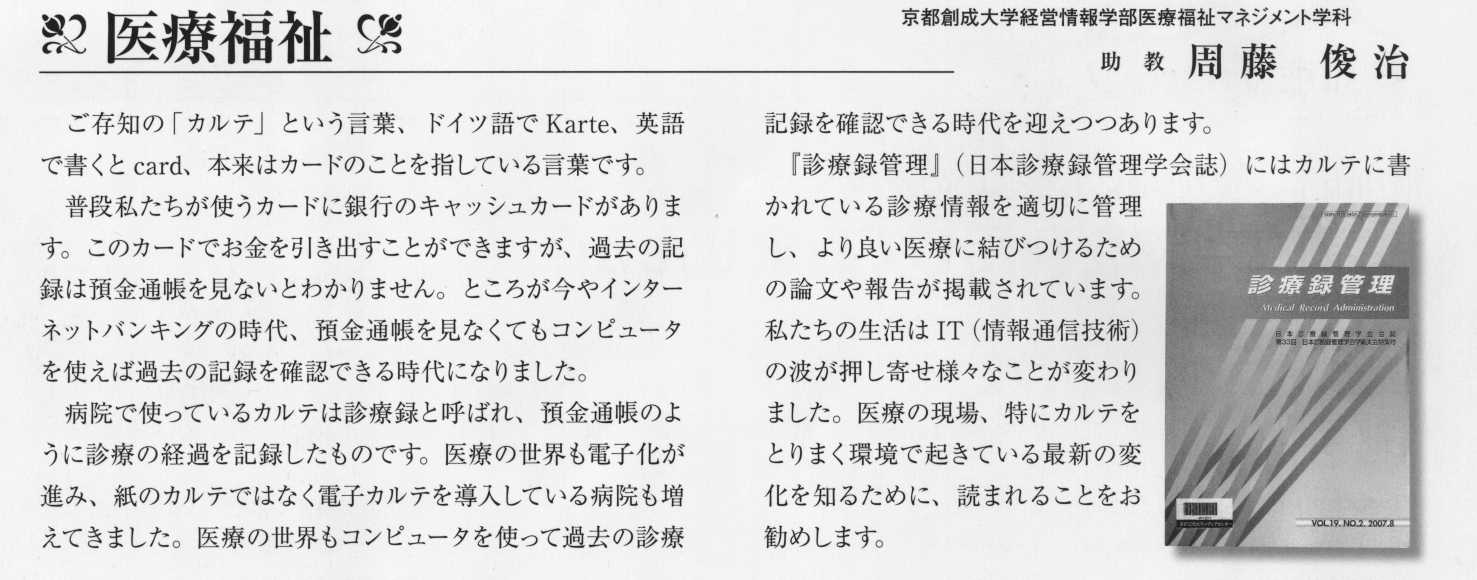
現在は電子カルテが多くの病院で導入されてきているが,「診療録」を電子化したものではなく,様々な機能を有する「電子カルテ」となっている
問3 診療録の電子化による恩恵で特に医療安全の上で効果が期待されるが,その理由は何故か考えよ
診療録の作成義務は医師法(資格法)で定められているところ診療録は医師法(資格法)において義務が定められているのがポイント(医療機関の話=医療法ではない)
医師法第24条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
同 第2項 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。
医師法で定めている理由としては、ともかく医療行為を行ったことの記録(というレベル)
故にキチンと記録しないと大変なことになる
医療事故と診療記録 : 関連する法律問題との関係から,前田 正一,日産婦誌,59(9) N-519-522,2007
http://www.jsog.or.jp/PDF/59/5909-519.pdfより引用
たとえば,岐阜地方裁判所昭和49年3 月25日判決は,一般論であるが,「…医師法第24条によれば,医師は患者を診察したときは診療に関する事項を記載した診療録(カルテ)を作成し,これを5 年間保存しなくてはならないところ,カルテの作成,保存を医師に義務づけたのは,医師の診療行為の適正を確保するとともに患者との関係で後日医師の診療をめぐって生起するかもしれない問題(再診療,医療費請求,医療過誤による損害賠償請求等)の法的紛争についての重要な資料となるものでありカルテに記載がないことはかえって診察をしなかったことを推定せしめるものとすら一般的にはいうことができるからである」と判示している.
電子カルテ
概念が広がっている 情報は「モノ」じゃない。物理的な制限は記録メディアに依存する。複製は簡単「電子カルテ」は「電子」化したことにより空間の制限を超えることができる
EMR(Electric Medical Record)施設内の診療録(カルテ)および診療情報を電子化し活用・・・法令上の枠組みの世界(情報の保存場所)
電子カルテは単なる記録するためのものではなく利便性の向上と活用できる環境へ

法的に保存義務のある文書等の電子保存の要件
電子媒体の保存の話 → 紙媒体ならば自然に出来ていた事柄・真正性の確保
(ア)故意または過失による虚偽入力、書換え、消去及び混同を防止すること。
(イ) 作成の責任の所在を明確にすること。
・見読性の確保
(ア) 情報の内容を必要に応じて肉眼で見読可能な状態に容易にできること。
(イ) 情報の内容を必要に応じて直ちに書面に表示できること。
・保存性の確保
電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中において復元可能な状態で保存することができる措置を講じていること。
<参考資料>
法令上作成保存が求められている書類(第9回医療情報ネットワーク基盤検討会(厚生労働省))
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0624-5e.html
他の医療関係記録に関する現行法令上の規定(抜粋)
(第10回「医療安全の確保に向けた保健師助産師看護師法等のあり方に関する検討会」(厚生労働省))
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/10/s1005-14b.html
診療で発生した情報(他医療機関)
医療機関の連携が活発に行われる中,情報も連携されることで診療がスムーズにEMR(Electronic Medical Record)・・・電子カルテ
EHR(Electronic Medical Record)・・・医療情報連携基盤
医療情報連携基盤(分散型)

医療情報連携基盤(クラウド型)

電子カルテの情報を施設を超えて活用するには,同一患者であっても期間毎にIDが発番されているため紐づけないと利用できない
地域医療連携を念頭においたシステムなので,地域外との連携が困難
健康・医療・介護情報利活用検討会 医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22119.html
診療により発生する医療費請求に関するデータ

国民皆保険制度として 1961年 昭和36年~ 強制加入保険制度であることから,大量のデータが発生する
問4 診療報酬に関するデータを利用するにあたって注意することは?
診療外で発生する情報
健診の情報や自身の健康データなどPHRの全体像(第44回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会)
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000891495.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23106.html
ICTがもたらす新たなアイテム
ICTが至る所に存在する時代
ウェアラブル端末
男性の命を救ったApple Watch、不整脈の専門医も太鼓判を押す「心電図」アプリ(マイナビ)
https://news.mynavi.jp/article/20240102-2853412/
ゲーム
ゲーム依存など健康を害するケースをよく耳にしますが,中には改善を促すケースもあります
ゲーム依存症 ~今話題の健康ワード!~(日本成人病予防協会)
https://www.japa.org/tips/kkj_1903/
ポケモンGO、鬱病も改善だぜ! 引きこもり7年間の少女進化…AR技術と精神疾患、学者に評価の動き(産経WEST)
https://www.sankei.com/article/20160806-37IUJFOPUVOYVMA2ZRFDEV7MXE/
ゲームは、毒にもなれば薬にもなる。(TELESCOPE Magazine ナノテクミュージアム(NANOTEC MUSEUM))
https://www.tel.co.jp/museum/magazine/019/report02_02/
過去のデジタル化の恩恵を振り返る(CT)
CT(Computed Tomography)は,アナログ写真と異なり,デジタルデータを用いてアナログでは撮影できない画像を可能にしたもの人が判断するためには多くの人にわかるような情報提供が必要.特別な知識などを必要としない可視化が必要なところは,データ発生量が増加しているだけに多くなっているように思う
問5 投影データを元にそれぞれのセルに入る数値を推定せよ
(数値は平均値=合計/セル数)である
被写体の断面をマス目の集合体と見做して計算
関連する法律 ガイドライン
医療における情報の取り扱いに関するところで取りまとめています刑法 刑事訴訟法
医療職者では医師,歯科医師,薬剤師,助産師の秘密漏示については刑法で定められています刑法
第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。2 宗教、祈祷とう若しくは祭祀しの職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
刑事訴訟法
第百五条 医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため、保管し、又は所持する物で他人の秘密に関するものについては、押収を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、押収の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。第百四十九条 医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。
刑法(e-gov)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045
刑事訴訟法(e-gov)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000131_20240515_505AC0000000028
資格法
医療職者の秘密漏示は刑法以外については資格法で定められています助産師 看護師 准看護師
第四十二条の二 保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなつた後においても、同様とする。保健師助産師看護師法(e-gov)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000203_20220617_504AC0000000068
個人情報保護法
「3年ごと見直し」が行われる法律科学技術の進展が利便性を向上させるが,新たな対応も必要となる






個人情報の保護に関する病院の義務と責任~個人情報保護法の施行へ向けて~ より
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの
2 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。
一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
3 この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
4 この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
5 この法律において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。
一 第一項第一号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
二 第一項第二号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
6 この法律において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。
一 第一項第一号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
二 第一項第二号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
7 この法律において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。
個人情報の保護に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057
3省2ガイドライン
医療情報システムに関するガイドライン医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 6.0版(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理に関するガイドライン 1.1版(総務省 経済産業省)
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/teikyoujigyousyagl.htmlこれから



地域と医療の統合に資する 情報活用の考え方 -不足の観点からみる医療2.10- より
法律やガイドラインは科学技術の進展に対応するためアップデータされていきます.
情報のデジタル化及び通信技術の進展により人類は自在に扱えるサイバー空間を形成し,これからも様々な場面に影響を及ぼしていきます.
大切なことは,社会的な課題の解決のために新たな技術を社会実装することで新たな課題が生じてしまう可能性があることです.
法的な枠組みで保たれていたものが新たな技術によりその枠組みを超えることにより,倫理での補完が求められる状況で,社会的な課題として認識されてから気付くケースが多い(普及した場合も普及しない場合も)